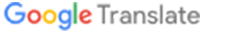第9回 美術館というライフライン 2025.01.21
あの日から今年で30年が経過するという。1995年1月17日、私が勤務していた兵庫県立近代美術館は阪神淡路大震災の直撃を受けた。当時私は京都に住んでいたから、震災の数日後に大阪に住む同僚とともに美術館に向かった。といっても阪急電車は夙川までしか通じておらず、夙川駅から先は3時間くらい歩いて美術館に向かったと記憶する。倒壊した家屋が道を塞ぎ、屋外で執り行われていたいくつもの弔いの傍らを通り過ぎた。重そうなスーツケースを引きずって逆向きに歩いてくる多くの人々の姿も記憶に残っている。苦労して美術館にたどりつくと彫刻室の窓ガラスは砕け散り、館内に入ると壁が平行四辺形の形に歪んでいた。実際、美術館は震災の中心に位置していたから、自衛隊から遺体安置所として使用できないかという問い合わせがあったことも後で聞いた。
それからの数か月、どのように過ごしたかは今でも夢のように感じられる。このような災害を人生の中で体験するとは想像もしていなかった。もちろん阪神間に所在する美術館は私たちだけではない。美術館が避難所になった施設もある。学芸員が24時間交代でレスキュー事業に派遣された美術館もある。県立美術館よりも市立美術館の職員の方が震災対応は苛酷であったように思う。泊りがけこそなかったが、私自身も多くの避難者がテント生活を営む公園に派遣されて連日救援物資の仕分けや配達に従事した。やがて三田を経由して北神急行経由で美術館に通えるルートが開通した。被災地への長い距離を満員の電車で移動する通勤者たちはいつも殺気立っていた。通勤の途中でいさかいや怒号にしばしば足を止めたことも強い印象として残っている
兵庫県立近代美術館では毎日朝と夕方、学芸員と保安員が一緒に館内を巡回して作品をチェックしていた。したがって学芸員は展示された作品と向き合うことを日課としていた。しかし当然ながら震災以来そのような機会は断たれた。3月中旬に被害状況の確認が終わると美術館の復旧工事が始まったため、収蔵庫に収められていた作品のうち約200点を京都国立近代美術館に一時的に疎開させ、保管をお願いすることになった。学芸員でありながら私たちは震災以来自分たちの美術館が収蔵する作品をまともに見ることができず、そもそも作品自体をほかの美術館に預けざるをえないような日々を送っていたのである。学芸員にとってはそれまで日常の一部であった作品との接触を一切断たれたまま、私たちは日々震災対応の仕事に追われた。ひたすら疲れる毎日であった。
余震も落ち着いた4月に入って、私たちは地元の兵庫銀行の協力を得て、ロビーを会場に所蔵作品の小規模な展示を行うことにした。板宿と長田と御影という三つの支店、いずれも甚大な被害があった地域である。銀行ロビーという会場の制約上、あまり大きな作品は展示できず、つかのまの展示であるから、毎年県内の公民館などで実施していた移動美術館のたびによく持ち出していたなじみのある小品を選んで会場に運んだ。箱を開梱し作品を取り出した時の感慨を私はいまだに忘れることができない。最初に述べたとおり、私は京都に住んでいたから通勤の苦労以外に生活の極端な変化はなかった。しかし震災からその日まで、私は美術作品を鑑賞の対象として目にすることがなかったのだ。作品を前にして私は美術と関わる日常が数か月ぶりに回帰したことの深い喜びに浸った。それから四半世紀が経過した今ですらその時の感銘を言葉で表現することは難しい。生き返ったような気分というのが一番近いかもしれない。そしてこのような感動を覚えたのは学芸員の私だけではなかったはずだ。震災の爪痕はなおもいたるところに残っていたが、多くの方が会場に足を運び、長い間、熱心に作品を見て下さった。たくさんの感謝の言葉を受けたことも覚えている。
10年ほど前に新しい県立美術館の計画が浮上して以来、私は美術館という施設がなぜ必要かを繰り返し説いてきた。この際にいつも最初に頭に浮かび、いまだに自分と美術とのつながりの核心と感じられるのがこの体験である。金具を捻れば蛇口から水が流れ、スイッチを押せば電灯が灯る。日常的な体験であればあるほど、私たちは自分たちがどれほどそれに依存しているかを理解することができない。水や電気は私たちに必要不可欠な生活ライフラインであるが、日常化しているがゆえに気づかない文化的、精神的なライフラインも存在するのではないか。かかるライフラインは失われて初めてその存在が意識される。震災を経て、私は美術、そして美術館がそのようなライフラインの一つであることをあらためて確信した。震災という非常時に作品を展示することに何の意味があるのか。当時よく聞かれた批判であるが、逆なのだ。非常時であるからこそ(もちろん人と作品の安全には十分な配慮をしたうえで)ライフラインとしての美術館は開かれなければならない。美術館ならぬ銀行のロビーで再会した金山平三や小磯良平のいつもと変わらぬ絵画を前に来場者と学芸員が等しく覚えた感動は、人が人間として生きるうえで美術館こそ死活的に重要な施設であるという、普段では思い及ぶことさえないであろう真実へと私をつないだ。